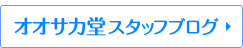2025/10/31
結論から言えば、「クエン酸が肝臓に悪い」その噂は科学的根拠に乏しい誤解です。
クエン酸は私たちのエネルギー代謝の要であるTCA(クエン酸)回路の中間体で、エネルギー産生に関わります。加えて、運動後の血中乳酸の回復が速まったとするヒト研究もあります。(参考文献:ヒトにおける レモン果汁およびクエン酸摂取 が運動後の血中乳酸濃度に及ぼす影響|国立研究開発法人科学技術振興機構 [JST])
一方で、サプリで一度に大量摂取したり、空腹時に粉末を飲んで胃を荒らしたりすると“肝臓が痛む”と錯覚するケースがあるのも事実。
本記事では「クエン酸が肝臓に悪い」と語られる5つの理由を検証しつつ、摂り方のコツとメリット・デメリットを整理します。
※本記事の内容は、診断や治療を目的とするものではありません。体調に不安がある場合は必ず医師にご相談ください。

【ガイド】オオサカ堂 コンテンツ制作チーム
おかげさまで28年間、安心信頼の個人輸入代行・オオサカ堂のコンテンツ制作チーム。専門知識を活かし、正確で分かりやすい情報発信を心がけています。一般社団法人 薬機法医療法規格協会のYMAA資格保有者が執筆。
目次
【結論】クエン酸が肝臓に悪いは科学的根拠のない誤解
「クエン酸は酸性だから、体に負担がかかり、肝臓に悪いのではないか?」 このような不安を抱えている方がいらっしゃいますが、まず結論から申し上げます。
その心配は、科学的根拠のない誤解です。
クエン酸は、レモンや梅干しなどに含まれる有機酸の一種で、私たちの体内でエネルギーを生み出す「クエン酸回路」という、生命維持に不可欠なサイクルの中核を担う成分です。
つまり、肝臓を含む全身の細胞が活動するための“ガソリン”を作るのに、なくてはならない存在です。
クエン酸が肝臓に悪いと言われる理由①「酸」のイメージが胃腸や歯への負担と直結
「酸」という言葉は、歯や胃を荒らすという強いイメージに繋がりやすいです。
実際に、高濃度のクエン酸には歯や胃に刺激を与える可能性がありますが、これは局所的な問題です。
この限定的なデメリットが、「体全体に悪く、肝臓にも負担をかけるはずだ」という、因果関係のない大きな話へと飛躍・誤解されているのが、噂が広まった一因です。
(参考文献:歯科疾患・歯科保健サービス等と就労環境との関わりに関する研究|厚生労働省)
クエン酸が肝臓に悪いと言われる理由②過剰摂取によるリスクとの混同
どんな成分でも、常識を超えた「過剰摂取」はリスクです。
クエン酸も例外ではなく、一度に大量に摂れば胃・食道などへの局所的な刺激が出ることがあります。
これはクエン酸に限らず、全ての食品に共通する考え方です。
ただし、通常の食品や製品表示の摂取目安の範囲で用いる限り、肝臓への負担を心配する必要は基本的にありません(クエン酸は食品中に広く存在し、長年の使用実績と安全性評価があるため)。
(参考文献:いわゆる「健康食品」に関するメッセージ|林野庁)
クエン酸が肝臓に悪いと言われる理由③アルコールと一緒に摂ると酔いが回る説
「レモンサワーは酔いやすい」という説から、肝臓への負担を連想するケースがあります。
しかし、クエン酸自体がアルコールの吸収を速めるという科学的根拠はありません。
実際には、酸味で飲みやすくなった結果、飲むペースが上がり多くのアルコールを摂取してしまうのが原因です。
肝臓への負担はアルコールによるもので、クエン酸のせいではありません。
クエン酸が肝臓に悪いと言われる理由④他の添加物(クエン酸ナトリウム等)との誤解
加工食品には、塩分を含む「クエン酸ナトリウム」が使われることがあります。
この塩分への注意が、クエン酸そのものへの注意だと誤解されている場合があります。
また、クエン酸入りの甘い飲料は、大量の糖分が脂肪肝のリスクとなります。
このように、一緒に含まれる糖分や塩分が、クエン酸の悪評に繋がっているのです。
(参考文献:クエン酸ナトリウムの副作用対策と効果の最大化につながる摂取方法の検討|一般社団法人日本スポーツ栄養協会)
クエン酸が肝臓に悪いと言われる理由⑤個人の体質に合わなかった体験談の拡散
「クエン酸を飲んだら胃が痛くなった」という個人の体験談が、ネットで拡散されることも原因です。
しかし、個人の体質に合わないことと、成分に毒性があることは全く別の話です。
胃への刺激といった局所的な反応が、肝臓へのダメージを示す証拠にはなりません。
一部の体験談が誇張され、多くの人に不必要な不安を与えているのです。
クエン酸を飲むメリット
「肝臓に悪い」という噂が誤解であることをご理解いただいたところで、クエン酸が持つ素晴らしいメリットについて見ていきましょう。
疲労回復効果は有名ですが、それ以外にも多くの体には嬉しい働きが報告されています。
疲労物質(乳酸)分解を助ける
クエン酸の最も代表的な効果は、疲労感の軽減です。体内でエネルギーを生み出す「クエン酸回路」は、その名の通りクエン酸が主役となるサイクルです。このサイクルが活発に回ることで、疲労の原因物質とされる「乳酸」が効率的に分解され、エネルギーとして再利用されます。運動後や疲れた時にクエン酸を摂取すると、体感としてスッキリするのはこのためです。肝臓はエネルギー代謝の中心的な臓器であり、クエン酸回路がスムーズに働くことは、肝臓の負担軽減にも繋がります。
(参考文献:クエン酸飲料は摂取タイミングにかかわらず、運動で蓄積した乳酸の迅速な除去を期待できる|一般社団法人日本スポーツ栄養協会)
食後血糖ピークを緩やかにする
近年注目されているのが、食後の血糖値上昇を穏やかにする効果です。食事と一緒にクエン酸を摂取することで、食べ物が胃から腸へ移動するスピードが緩やかになり、糖の吸収が穏やかになることが研究で示唆されています。
(参考文献:様々な食品素材が食後高血糖抑制に及ぼす影響の検討|同志社大学)
鉄・ミネラル吸収を1.3〜1.5倍に
クエン酸には、ミネラルを掴んで体に吸収しやすくする「キレート作用」があります。特に、女性に不足しがちな「鉄」や「カルシウム」は、単体では吸収されにくい性質がありますが、クエン酸と一緒に摂ることで、その吸収率が著しく向上します。研究によっては、吸収率が1.3倍〜1.5倍に高まったという報告もあります。
ミネラルは肝臓を含む全身の酵素が正常に働くために不可欠です。クエン酸は、他の栄養素の働きを助ける、縁の下の力持ちでもあるのです。
(参考文献:オート麦ベースの飲料における鉄のバイオアベイラビリティの改善:クエン酸添加、脱フィチン化、鉄補給の複合効果|PubMed)
クエン酸摂取のデメリットと注意点
クエン酸は基本的に安全な成分ですが、デメリットが全くないわけではありません。
ただし、そのリスクは「肝臓」ではなく、主に「歯」と「胃腸」に関連するものです。正しい知識で、これらのデメリットをしっかり回避しましょう。
胃弱体質は空腹時NG
クエン酸は酸性の物質ですので、空腹時に高濃度のものを摂取すると、胃の粘膜を刺激して、痛みや不快感を引き起こすことがあります。特に、もともと胃が弱い、胃酸過多の傾向があるという方は注意が必要です。
エナジードリンク併用で糖質過多になりやすい
クエン酸は、多くのエナジードリンクや清涼飲料水に、酸味料や疲労回復成分として添加されています。これらの飲料は、爽やかな酸味で飲みやすい反面、驚くほど多くの糖分(果糖ぶどう糖液糖など)が含まれていることがほとんどです。
クエン酸を摂る目的でこれらの飲料を常用していると、知らず知らずのうちに大量の糖質を摂取することになり、肥満や脂肪肝のリスクを著しく高めてしまいます。
「クエン酸 肝臓に悪い」に関するよくある質問(FAQ)
Q1.クエン酸は毎日取っても安全?
はい、1日の摂取目安量(5〜15g程度)を守れば、毎日摂取しても安全です。
クエン酸は体内で速やかに代謝・消費され、蓄積することがないため、継続的に摂取しても問題ありません。
むしろ、エネルギー産生を日々サポートするという意味で、毎日の摂取が推奨される成分でもあります。ただし、体調に合わせて量を調整することが大切です。
(参考文献: クエン酸のよくあるご質問 | 一般向け製品情報 | 健栄製薬)
Q2.天然のレモンとサプリメントに違いはありますか?
化学的な「クエン酸」という物質に違いはありません。しかし、レモンにはクエン酸以外にも、ビタミンCやポリフェノール、食物繊維といった多様な栄養素が含まれている点が大きな違いです。
レモンなどの食品
多様な栄養素をバランス良く摂取できる。
サプリメント
クエン酸を効率的かつ安価に、決まった量だけ摂取できる。
目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。例えば、総合的な健康効果を期待するなら食事にレモンを、運動後の疲労回復など特定の目的にはサプリを、といった形です。
Q3.医薬品との飲み合わせは?(肝炎薬・利尿薬ほか)
クエン酸には、尿をアルカリ性に傾ける作用があります。尿のpHが変化すると、一部の医薬品の吸収や排泄に影響を与え、薬の効果が強まったり弱まったりする可能性があります。
必ず事前に医師または薬剤師に相談してください。自己判断での併用は避けるべきです。
(参考文献:薬物動態学|国立研究開発法人科学技術振興機構 [JST])
まとめ:過剰摂取しない限りクエン酸が肝臓に悪いということはない
この記事では、「クエン酸は肝臓に悪い」という噂の真相について、5つの理由と科学的な視点から多角的に解説しました。
「クエン酸が肝臓に悪い」という言葉だけを鵜呑みにせず、その性質を正しく理解し、適切な量と方法で摂取すること。
それが、クエン酸の素晴らしい恩恵を受け、健康な毎日を送るための鍵となります。

「クエン酸=体に悪い」という誤解を解くため、この記事を制作しました。私たちは、噂を否定するだけでなく、エネルギー代謝の要である「クエン酸回路」の仕組みを丁寧に解説することに注力しました。この記事で、本当の働きを知り、安心してご活用いただければ嬉しいです。監修・オオサカ堂コンテンツ制作チーム
関連記事
-

-
【2026年最新】ウィダーインゼリーが体に悪いと言われる理由5選!風邪の時にはどのタイプが良いか徹底解説
結論から言えば、ウィダーインゼリーのようなゼリー飲料はは忙しい時のカロリー源として便利ですが、主食代わりに置き換え続けると糖質過多による血糖値スパイク、たんぱく質・食物繊維不足、酸性度と添加物による歯 …
-

-
どくだみ茶が肝臓に悪いと言われる理由5選!体臭への効果などについて解説
どくだみ茶が肝臓に悪いという噂がありますが、現在明確な根拠などは示されておらずSNSを中心に拡散されてしまった偽情報の説が濃厚です。 むしろ、ドクダミ(Houttuynia cordata)茶由来の成 …
-

-
杜仲茶が肝臓に悪い(危険)と言われる理由5選!効能について解説
結論から言えば、それは科学的根拠に乏しい“真逆”の噂です。 むしろ杜仲茶に含まれるポリフェノール「アスペルロシド」は胆汁酸の分泌を促し、肝臓や筋肉、褐色脂肪の代謝スイッチをオンにすることが報告されてい …
-

-
カモミールティーが肝臓に悪いと言われる理由5選!効能から注意すべき副作用まで薬剤師が解説
健康のために選んだその一杯が、まさか「毒」だったなんて。 そんな不安で、せっかくのリラックスタイムが台無しになっていませんか? 一日の終わり、心をほどくために淹れるカモミールティー。 その優しい香りに …
-

-
【2026年最新】スペ110とは?見た目や計算してわかる美容体重・シンデレラ体重と比較痩せ基準
スペ110 はスマートに見える反面、BMI18.5 未満=やせ という低体重域に入りやすい値です。 令和5年の国民健康・栄養調査では 20〜30 代女性の20.2%が低体重に分類されており、 …