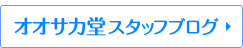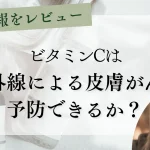2024/07/17
こんにちは。オオサカ堂です。
もうすぐ世間は夏休み。あちこちお出かけが増えてくる季節です。
せっかくの旅行や遊びの時間が、乗り物酔いで台無しになるのはもったいない!
ということで今回は、乗り物酔い対策についてご紹介します。
乗り物酔いを起こす仕組み

そもそも、どうして人は乗り物に乗ると酔うのでしょう。
それは、脳の混乱と自律神経のバランスの崩れが原因。
乗り物酔いは、車や船、電車など、乗り物の動揺(揺れ)によって起こる症状で、医学的には「動揺病」と呼ばれます。
人は、目からの情報、耳からの情報、体(筋肉など)が受ける情報を統合して、自分の空間識(自分と周りとの位置関係)を作っていますが、不規則または急激な揺れや加減速によって脳が混乱し、自律神経が異常に興奮状態になって、めまいや吐き気、嘔吐、胃のむかつき、冷や汗などの症状を引き起こします。
乗り物酔いをする人・しない人

子供と大人では、子供の方が乗り物に酔いやすいとされています。これは、子供の方が脳(前庭小脳)が発達段階で、揺れに過敏に反応するため。
大人になるにつれ、刺激に対する反応が鈍くなるので、乗り物酔いをしにくくなるといわれていますが、それでもやっぱり酔いやすい人・酔いにくい人がいます。
それには、体質の違いが考えられます。
先に述べたように、乗り物酔いは自律神経のバランスの崩れが原因。アレルギー持ちの方、低血圧気味の方は、自律神経系のトラブルが関係しているので、酔いやすい傾向にあるといえます。また、乗り物酔いの症状として胃の不快感があり、お腹が普段から弱い人も乗り物酔いになりやすいとされています。
乗り物酔いを防ぐには
酔いやすい人は特に、車や飛行機での移動となると準備の段階からげんなり。
できれば酔わずに乗り切りたい!
そのため、以下の対策を取ることをおすすめします。
・前日は早めに休んでしっかりと睡眠をとる
・乗る前の空腹・食べ過ぎを避ける
・締め付ける洋服は避けて、楽な格好をする
・視線が固定されると酔いやすいので、本やスマホは見ない
・不安やストレスで自律神経が乱れやすくなるため、「酔わない」と思い込む
・頭が過度に揺れないよう、ネックピローやヘッドレストなどをする
・バスの場合は、(比較的揺れが少ない)車輪がない中央部の席に座る
それでも乗り物酔いになってしまったら
元も子もありませんが…
どんなに対策をとっても、酔ってしまうことはあります。
そんな時はこれで乗り物酔いの軽減を。
・目を閉じる。または遠くを眺める
・(可能であれば)窓を開けたり降りたりして、新鮮な空気を吸う。風に当たる
・座っている状態であれば、横になるなど楽な姿勢になる
・襟、ベルトなどの締め付けを緩める
・吐きそうになったら我慢せずに嘔吐する
・酔い止めの薬を飲む
・飴やチョコ、梅干し、ガムなど、酔い止めに効くとされる食べ物を摂取する
乗り物酔いの対策アイテム
おでかけの機会が増えるこれからの季節。
乗り物酔いで楽しさが半減…とならないよう、しっかり対策を立てましょう。
オオサカ堂でした!
関連記事
-

-
嫉妬とうまく付き合う「ジェラシーマネジメント」
「彼女と仲良くしてほしくない」「なんで自分じゃないの」「友達が持っているあの車いいな」「あの人みたいになりたい」 恋人や好きな人に抱く焼きもち、仕事や友人へのライバル心、はたまた芸能人に対しての羨望な …
-

-
海外論文レビュー「ビタミンCは皮膚がんの予防に効果があるのか?」
ビタミンCは美容と健康に欠かせない栄養素として広く知られています。特に、コラーゲン生成を助ける役割や抗酸化作用による老化防止効果が注目されています。そんなビタミンCですが、美容効果だけでなく、皮膚がん …
-

-
秋の味覚!キノコの栄養素に迫る
低カロリーで、ダイエットによいとして特に女性に人気のキノコ。でも、その恩恵はダイエットだけのもの?どれを食べても一緒?今回は、キノコが持つ栄養についてご紹介します。 目次キノコに共通する栄養素不溶性食 …
-

-
紫外線を防ぐ色ランキングTOP5! 意外と知らないUV対策カラーについて解説
紫外線は、私たちの肌や髪にさまざまなダメージを与える大きな原因のひとつです。 特に日常の外出や通勤、レジャーなどで気がつかないうちに受けている紫外線は、シミ・シワ・そばかすなどの肌トラブルを引き起こし …
-

-
「まぶたのピクピク」と「こむら返り」がどっちも治った話
こんにちは。今日のテーマは骨格筋のバグである「けいれん」について。学生時代から足をつったり、まぶたのけいれんを起こしたりしやすかった私が、あるモノのおかげですっかり克服できた話をしたいと思います。 目 …