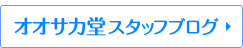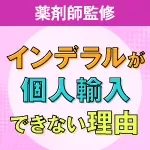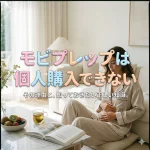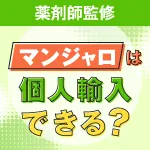こんにちは。今日のテーマは、軽視すると命に関わる「熱中症」について。熱中症は、昨年の救急搬送が9万人を超えており、年齢や性別を問わず誰もがかかりうるものです。本コラムでは熱中症の脅威についてとともに、どのように予防すれば命を守れるかを解説したいと思います。まだまだ続く猛暑に備えて、ぜひお読みください。

【監修】オオサカ堂 薬事チーム
薬学分野に精通した有資格者が豊富な経験を活かして医薬品情報を厳格にチェック。分かりやすい薬学的アプローチで解説しています。
当コラムに関するご注意点
当記事は薬剤師による意見や助言等を含みます。情報の信頼性や不適切な表現がないか等、細心の注意を払って確認しておりますが、掲載内容については読者個々の健康管理上において何らかの保証をするものではありません。
当記事における医薬品に関連する情報については、特定の商品を指すものではなく、成分の説明や解説をもって公衆衛生の向上及び増進につながることを目的としています。
当記事におけるオオサカ堂公式サイトへの各種リンクは読者利便性のために設置しており、特定商品の誘引を企図するものではありません。また当記事内の全てのリンクにおいて、一切の送客手数料等は発生しておりません。
当記事内容は執筆時点の情報です。掲載後の状況により、予告なしに内容を変更、更新する場合があります。
前各項に関する事項により読者に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切の責任を負うものではありません。
目次
東京はどんどん暑くなっている
まず知っておきたいのが、日本の夏の異様な暑さです。過去30年間における、東京都の8月の最高気温をグラフにしてみました。
8月の最高気温は、1993年が28℃なのに対して、2023年は34.3℃と、30年間でなんと6℃以上も高くなっています。東京に限らず日本全国で夏の気温は上昇傾向です。体感としても夏の暑さが年々厳しくなっている気がしていましたが、数字にもちゃんと現れています。また後述しますが、日本の夏は湿度と輻射熱(物体から発する熱)も高いことから、熱中症にかかりやすい気象条件が揃っています。
今年は「10年に1度の猛暑」に
環境省の発表によると昨年の熱中症による救急搬送人員数は累計91,467人となっており、これは平成20年の調査開始以降2番目に多い値だそうです。ところが今年は「10年に1度の猛暑」などと報道されているように、昨年以上に厳しい暑さが続いており警戒が必要です。
また今年の全国の熱中症による救急搬送状況(7/8~7/14速報値)を見ると、約半分の人が住居(敷地内の全エリア)で熱中症になり搬送されているように、家にいても熱中症には注意が必要なことが分かります。
今さら聞けない「熱中症」について
熱中症は「暑熱環境にいる/いたことよって起こる諸症状の総称」をあらわします。具体的な症状は、めまい、失神、高熱、大量の汗、筋肉の硬直、こむら返り、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、意識障害、けいれんなど色々あります。
めまいや頭痛などの症状は日頃から経験しやすい症状のため、熱中症の症状として自覚しにくいのがネックですが、夏の間はこのような症状を軽視せず早めに対策した方がいいでしょう。
また熱中症には、最新の診断ガイドライン上「Ⅰ度~Ⅳ度」までの重症度分類があり、Ⅲ度以上では速やかに処置や治療が必要なケースも存在します。対応が遅れた場合に後遺障害が残ったり命を脅かしたりする危険性があります。事実、熱中症による死亡者数は上昇傾向なのです。
日本の夏は暑すぎますし、かといって夏の間だけ日本から離れることができるわけでもないので苦しいところですが、「暑すぎて死ぬ」はあり得るということを知っておく必要があります。
正しい予防対策で命を守ろう
ここからは、日本の夏の脅威「熱中症」から命を守るための予防法について解説します。熱中症診療ガイドライン2015/2024によると、熱中症にかかりやすい傾向として以下のような特徴が挙げられています。
時期:梅雨が明けたあとの7月中旬~8月上旬がピーク
時刻:正午(12時)~15時前後の日中に多い
発生時の状況:若年ではスポーツ、壮年では肉体労働によることが多い
特に気をつけるべき条件:高温多湿環境、エアコンがない(使用していない)、高齢者、子ども、基礎疾患のある人、特定の薬を服用している人、水分摂取量が少ない人
スポーツや労働による熱中症は「労作性熱中症」と呼び、もともと健康な人が短時間でなる傾向があり、回復が早いとされています。労作性熱中症のなりやすさに性差があるかどうかは分かっていませんが、男性の方が行動性として暑熱環境や労作環境に曝露しやすく、より注意が必要と考えられています。
一方、日常生活のなかで起こる「非労作性熱中症」は、男女ともに高齢になるほど起こりやすく、また気づかぬうちに進行するために対処が遅れて重症化しやすい傾向があります。
有効な予防対策を講じることで、かかるリスクを最小化するだけでなく重症化のリスクも下げることができるため、ぜひ実践しましょう。
屋内での予防
・エアコン、扇風機をつける
・遮光カーテン、すだれを設置する
屋外での予防
・日陰に移動する
・日傘や帽子を着用する
・はげしい運動を避け、休憩を多くとる
場所を問わずの予防
・のどが渇いていなくても、一気にではなくこまめに水分補給をする
・通気性や放熱性のある衣服を着用する
・保冷剤、濡れタオル、ハンディ扇風機などで体を冷やす
水分補給に関する注意点
・健康な成人は、屋内・屋外を問わず1日最低でも500~1,000mL飲む
・暑熱環境下や労作中(スポーツや労働)は、20分おきに200mL程度飲む
・真水ではなく塩分も 0.1~0.2% 程度とる
(例)1リットルの水分に対して食塩は1~2g
・経口補水液は水、電解質、糖分のバランスに優れている
・スポーツドリンクは水、電解質を効率よく摂れる反面、糖分過多に注意が必要
・アルコール、カフェイン含有飲料は水分補給にカウントしない
熱中症予防のための資料(厚労省)などを元に作成
熱中症警戒アラートと暑さ指数(WBGT)
熱中症警戒アラート
熱中症の危険性に対する「気づき」を促すものとして、環境省が「熱中症警戒アラート」を発表しています。熱中症警戒アラートは、暑さ指数(WBGT)を指標として発令されます。下図は、2024年7月29日の熱中症警戒アラートの様子です。
このように、都道府県別に熱中症の危険性をレベル別で毎日発表しており、衣服やスケジュールを決める上で参考になります。
暑さ指数(WBGT)
暑さ指数とは、湿球黒球温度(WBGT:WetBulb Globe Temperature)のことで、熱中症に関与する気温、湿度、輻射熱、気流などの要素から総合的に算出される数値です。同じ気温であっても、湿度や日射量の違いによって熱中症のかかりやすさには大きな差が出ることから、1950年代にアメリカで発案されました。
熱中症の危険度がかなり高まる「暑さ指数31」以上では、熱中症警戒アラートマップ上でも赤、紫、黒で表示されます。この指数を観測する地域では特に労作性・非労作性を問わず熱中症の危険度が非常に高いため、前述したような予防対策をもれなく行うとともに、周囲の人とも互いに声を掛け合って命を守りましょう。「とにかく無理をしない」という意識を常に持っておくことが大切だと思います。
いかがでしたでしょうか。熱中症警戒アラートについては、LINEでアラート通知を受け取れるサービスなどもあるようです。ぜひこういったものも活用しながら、猛暑の夏を安全に乗り切っていきましょう!
\夏の対策としてコチラもぜひ!/
参考情報
熱中症予防情報サイト|環境省
https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_report.php
熱中症予防のための情報・資料サイト|厚労省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
熱中症診療ガイドライン2015/2024|日本救急医学会
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pdf/heatstroke2015.pdf
https://www.jaam.jp/info/2024/files/20240725_2024.pdf
関連記事
-

-
【薬剤師監修】EXP(期限表示)とは?海外医薬品の消費期限と見方ついて徹底解説
海外医薬品を購入するときに必ず目にする「EXP」表記。 実は日本の「消費期限」や「使用期限」とは少し違ったルールで管理されていることをご存じでしょうか。 特に初めて海外医薬品を使用する際には、EXPの …
-

-
【薬剤師監修】インデラルは個人輸入できない?オオサカ堂で注文できない理由について解説
インデラルは、高血圧や狭心症などの治療に用いられる薬です。 その一方で、最近では人前で発表する際などに起こる動悸や手・声の震えといった、「あがり症」の症状をやわらげる薬として注目されています。 こうし …
-

-
モビプレップは個人購入できる?市販もなく代用もできない理由を解説
「モビプレップは通販サイトで購入できないか?」と考えたことはありませんか。モビプレップは、大腸内視鏡検査前に腸の中をきれいにするために医療現場で使われる下剤です(参考文献:モビプレップ配合内用剤添付文 …
-

-
【薬剤師監修】私たちオオサカ堂でマンジャロ(チルゼパチド)は個人輸入できる?正規入手方法について
「最近よく聞く『マンジャロ』って、オオサカ堂で注文できるかな?」そうお考えの読者の方もいらっしゃるかもしれません。 マンジャロは持続性GIP/GLP-1受容体作動薬として注目されていますが、その入手方 …
-

-
【薬剤師監修】メトホルミンによる下痢はいつまで続くのか?対策方法を徹底解説
メトホルミンは、2型糖尿病の薬物療法では多くの国で「第一選択薬」として用いられる血糖降下薬です。一方で、副作用として下痢を起こしやすい薬としても知られています。(参考文献:PMDA「医療用医薬品 : …