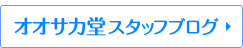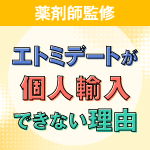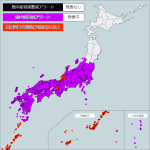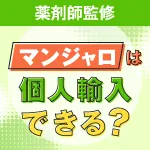2025/08/28
メトホルミンは、2型糖尿病の薬物療法では多くの国で「第一選択薬」として用いられる血糖降下薬です。一方で、副作用として下痢を起こしやすい薬としても知られています。(参考文献:PMDA「医療用医薬品 : メトグルコ」添付文書 )
多くの場合は、飲み始めの1〜2 週間で治まりますが、今まさに症状に苦しむ患者さんにとっては一刻も早く解決策が欲しいところ。
本記事では薬剤師監修のもと、症状が続く期間の目安と“今すぐ”できる対策について解説します。

【監修】オオサカ堂 薬事チーム
当社に在籍する薬剤師が豊富な経験を活かして医薬品情報を厳格にチェック。分かりやすい薬学的アプローチで解説しています。一般社団法人 薬機法医療法規格協会のYMAA資格保有。

【ガイド】オオサカ堂 コンテンツ制作チーム
おかげさまで28年間、安心信頼の個人輸入代行・オオサカ堂のコンテンツ制作チーム。専門知識を活かし、正確で分かりやすい情報発信を心がけています。YMAA 資格保有者が執筆・監修。
目次
メトホルミンによる下痢はいつまで続く?【症状のピークと平均期間】
メトホルミンは、約4割の方が副作用として下痢を経験します。服用し始めてから、「この下痢は一体いつまで続くのか」と不安に思う方も多いと思います。
結論から言うと、この症状は一過性であることが多く、体が薬に慣れるにつれて軽快していくケースが大半です。
具体的には、メトホルミンが原因の下痢は、服用開始後1〜2週間が症状のピークとなり、その後は徐々に落ち着いていきます。
この期間はあくまで目安です。もし1日に複数回の下痢が続く場合や、発熱・嘔吐・激しい腹痛などを伴う場合は、メトホルミンによる乳酸アシドーシスや、メトホルミンとは関係ない病気(感染性胃腸炎など)も考えられます。
我慢せず、早めに担当医へ連絡しましょう。
(参考文献:メトグルコ錠|インタビューフォーム)
メトホルミンによる下痢の対策方法① 食直前・食後に服用する
メトホルミンによる下痢や吐き気といった消化器症状を抑えるためには、「服用タイミング」に気を付けることが大切です。
メトホルミンは空腹時に服用すると、胃酸の刺激や腸の壁への直接的な負担が増え、副作用を起こしやすくなることが報告されています。
このためメトホルミンを医師が処方する際には、通常「食直前」か「食後」に服用するように指示が出ます。食事の直前や、食後に服用することで、食べ物がクッションとなり、胃腸への刺激を和らげることができるためです。
医師の指示を確認し、服用タイミングを守って飲むことがポイントです。
(参考文献:メトグルコ錠|患者向医薬品ガイド)
メトホルミンによる下痢の対策方法② 消化の良い食事を心がける
メトホルミンの服用により胃腸がデリケートになっている時期は、食事内容が下痢の症状を増幅させてしまうことがあります。
特に症状のピークである最初の1〜2週間は、意識的に消化の良い、胃腸に優しい食事を心がけましょう。油、加工肉、アルコール、辛い・冷たい食べ物などは胃腸の刺激となりやすいため、避けるのが良いでしょう。
また、下痢が続くと体内の水分が失われ、脱水症状を起こしやすくなります。
食事だけでなく、こまめな水分補給も非常に重要です。
メトホルミンによる下痢の対策方法③ 少量から飲み始める
メトホルミンの下痢は、服用する量が多いほど起こりやすくなる「用量依存性」の副作用です。
そのため、海外では Start low, Go slow(少量から開始、ゆっくり増量)というアプローチが提唱されており、国内でも、副作用を最小限に抑えるために、少ない量から治療を開始し、体の様子を見ながら段階的に増量していく「漸増投与」が推奨されています。
もし下痢がひどい場合は、自己判断で減らすのではなく、医師に相談して増量のペースを緩やかにしてもらうなどの調整が可能です。
(参考文献:PMDA「医療用医薬品 : メトグルコ」添付文書 )
メトホルミンによる下痢の対策方法④ 整腸剤を併用する
食事や服用タイミングを工夫しても下痢が改善しない場合、医師の判断で整腸剤が一緒に処方されることがあります。
メトホルミンによる下痢の一因として、腸内フローラ(腸内細菌叢)のバランスが一時的に変化することが考えられており、整腸剤の併用で軟便が改善したという報告もあります。
整腸剤は下痢止めとは異なり、腸の動きを無理に止めるのではなく、腸内細菌のバランスを改善するものです。
整腸剤と一口に言っても、ドラッグストアなどで購入できる市販薬から、乳酸菌飲料、発酵食品など、医薬品から食品まで多岐に渡り、腸内との相性も人それぞれ違います。医師や薬剤師に相談しながら最適な整腸剤を見つけることが大切です。
なぜ起こる?メトホルミンで下痢になる原因
「そもそも、なぜメトホルミンで下痢になるの?」という原因を知ることで、漠然とした不安を和らげることができます。
メトホルミンによる下痢は、薬が体に合わない「毒」として作用しているのではなく、薬が持つ本来の作用が副次的に消化器症状として現れているものです。
まだ原因の全ては分かっていないものの、主に以下の3点が考えられています。
腸内細菌叢の急激な変化
メトホルミンは腸内フローラに影響を与え、長期的には善玉菌を増やすなど良い変化をもたらすことが報告されています。しかし、服用初期には腸内環境が急激に変化するため、一時的にバランスが乱れ、ガス(おなら)が増えたり下痢になったりすることがあります。
(参考文献:3分でまるわかり!「メトホルミン」で下痢が起こるのはなぜ?|m3.com)
腸管でのグルコース吸収抑制
メトホルミンの主要な働きの一つが、小腸でのブドウ糖の吸収を抑えることです。これにより、吸収されなかった糖が腸管内の浸透圧を高め、それを薄めるために水分が腸に引き込まれ、便が緩くなります。
用量依存の粘膜刺激
高用量のメトホルミンを一度に服用すると、腸の粘膜への直接的な刺激となり、腸の運動が過度に活発になることがあります。これが、少量から開始する理由の一つです。
【乳酸アシドーシスへの注意】
頻度は極めて稀(0.005%程度)ですが、メトホルミンには「乳酸アシドーシス」という重篤な副作用があります。肝機能障害や腎機能障害のある方、飲酒量の多い方、脱水症状や体調不良などの状況下で特に注意が必要となります。単なる下痢ではなく、激しい腹痛・嘔吐・強い倦怠感・過呼吸などを伴う場合は、直ちに服用を中止し、医療機関を受診してください。
(参考文献:メトホルミンのすすめ|新潟市医師会)
メトホルミンに関するよくある質問
Q1. 下痢止め(市販薬)を自己判断で飲んでもいいですか?
A.原則として自己判断での服用は推奨されません。特に強力な止瀉薬(下痢止め)は、腸の動きを強制的に抑え込むため、血糖コントロールに影響を与えたり、感染性胃腸炎だった場合に菌の排出を妨げたりする恐れがあります。症状がひどい場合は、まず担当医やかかりつけ薬剤師などに相談し、用量調整、食事改善、整腸剤の導入などの対応を検討しましょう。
Q2. 薬に慣れると、下痢は本当に治まりますか?
A.はい。多くの患者さんで、服用開始後2週間以内に腸が薬の作用に順応し、下痢は自然に軽減・消失します。体が薬に適応していく過程で起こる一過性の症状であることがほとんどです。ただし、2週間以上経っても日常生活に支障をきたすような下痢が続く場合は、メトホルミンが体質的に合わない、あるいは別の疾患(感染症、過敏性腸症候群、糖尿病性下痢など)が隠れている可能性も考えられます。我慢せずに医師に伝え、必要に応じて検査を受けることを推奨します。
Q3. 自己判断で服用を止めていいですか?
A.自己判断で服用を中止することは原則としてやめてください。メトホルミンは血糖値を安定させ、糖尿病の合併症(心血管疾患や神経障害、腎症など)を防ぐための重要な薬です。処方薬を中止すべき場面などについては、担当医から個別に指示が出ることが多いです。まずは指示内容を確認しましょう。
まとめ:メトホルミンの下痢はよくある副作用。不安な時は必ず医師に相談を
「メトホルミンによる下痢はいつまで続くのか」という疑問に対する答えは、「1〜2週間がピークで、1ヶ月以内には軽快することが多い」というのが一つの目安です。
このつらい期間を乗り切るための対策は、①食直前/食後服用、②消化に良い食事、③少量からの開始、④整腸剤の併用です。
重要なのは、下痢を恐れて自己判断で薬を中断しないことです。
ただし、1日に複数回以上の水様便が3日以上続く、血便・発熱・激しい腹痛を伴う場合は、医療機関へ連絡してください。
メトホルミンによる下痢は、多くの人が経験する「よくある副作用」ですが、長く続くものではなく、工夫により軽減できます。我慢することなく、医師や薬剤師、管理栄養士などの指導を受けながら乗り越えていきましょう。

糖尿病薬物療法のゴールドスタンダードでもある血糖降下薬のメトホルミンについて解説しました。メトホルミンは1960年頃に誕生した薬剤で、長い使用実績と多くの研究の成果からさまざまな作用や副効用が見つかっており、現在も非常に注目されている成分のひとつです。糖尿病治療は長きに渡るため、服用する薬に対する不安な気持ちは少しでも解消しながら、病気と向き合い正しい治療を続けていくことが大切です。本稿がその一助になれば幸いです。
監修・オオサカ堂 薬事チーム
関連記事
-

-
【薬剤師監修】私たちオオサカ堂でイソトレチノイン(アキュテイン)は注文できる?個人輸入禁止の理由について
オオサカ堂でイソトレチノイン(アキュテイン)は注文できません。 イソトレチノインは、「数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品」として定められているため、処方せん等を含む輸入確認書類なしで個 …
-

-
【薬剤師監修】エトミデートの個人輸入は禁止。ゾンビタバコと呼ばれる理由も解説
エトミデートの個人輸入は、2025年5月に法律で禁止されたため、できません。SNSやニュースで「ゾンビタバコ」という言葉を知った方もいるのではないでしょうか。「ゾンビタバコ」とは、電子タバコ用リキッド …
-

-
【薬剤師執筆】搬送9万人超!猛暑の脅威から命を守る
こんにちは。今日のテーマは、軽視すると命に関わる「熱中症」について。熱中症は、昨年の救急搬送が9万人を超えており、年齢や性別を問わず誰もがかかりうるものです。本コラムでは熱中症の脅威についてとともに、 …
-

-
【薬剤師監修】私たちオオサカ堂でマンジャロ(チルゼパチド)は個人輸入できる?正規入手方法について
「最近よく聞く『マンジャロ』って、オオサカ堂で注文できるかな?」そうお考えの読者の方もいらっしゃるかもしれません。 マンジャロは持続性GIP/GLP-1受容体作動薬として注目されていますが、その入手方 …
-

-
【薬剤師監修】睡眠薬マイスリー(ゾルピデム)は個人輸入・通販NG!トラブル回避の正しい入手方法とは
「海外通販で マイスリー 個人輸入 すれば安く手に入るのでは?」 そう考えて検索している方は要注意です。 マイスリー(一般名ゾルピデム)は第3種向精神薬に分類され、日本では麻薬及び向精神薬取締法の規制 …