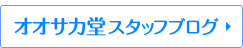2026/02/23
甘酒が肝臓に悪いかどうかは飲み方や飲む量に依存します。
栄養豊富で「飲む点滴」とも言われる甘酒ですが、「肝臓に悪い」という情報を目にして不安を感じていませんか。
健康のために始めた習慣が、逆に体の負担になっているとしたら心配ですね。
甘酒が肝臓に悪いと言われる原因は、酒粕甘酒にわずかながら含まれるアルコールや、米麴甘酒に多く含まれる糖質に由来します(参考文献:麴甘酒の過剰摂取による安全性検証試験)。
この記事では甘酒が肝臓に悪いと言われる理由と、甘酒のメリットや正しい選び方、安全な摂取量について、薬剤師の視点から解説します。

【監修】オオサカ堂 コンテンツ制作チーム
おかげさまで28年間、安心信頼の個人輸入代行・オオサカ堂のコンテンツ制作チーム。専門知識を活かし、正確で分かりやすい情報発信を心がけています。 薬剤師資格保有者が監修。
目次
- 【結論】甘酒が肝臓に悪いかは飲み方と甘酒の「種類」で決まる
- 甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選①酒粕(さけかす)甘酒に含まれる「微量アルコール」
- 甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選②米麹(こめこうじ)甘酒の「糖質」による脂肪肝リスク
- 甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選③「血糖値の急上昇(血糖値スパイク)」が招くインスリン抵抗性とNASH
- 甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選④「カロリー過多」で飲む点滴が天敵に!糖尿病や肥満のリスク
- 甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選⑤既存の肝疾患や糖尿病を悪化させる懸念
- 甘酒や酒粕のすごい効果!デメリットだけじゃない飲む点滴と言われるメリットを紹介
- 甘酒を飲んではいけない病気は?脂肪肝や糖尿病が気になる人の正しい選び方・飲み方
- 研究データから導く甘酒の「安全な1日の摂取量」と「飲むタイミング」
- 「甘酒 肝臓に悪い」に関するよくある質問(Q&A)
- まとめ:甘酒は健康に悪いは嘘!適量で点滴に飲みすぎれば天敵に
【結論】甘酒が肝臓に悪いかは飲み方と甘酒の「種類」で決まる
甘酒が肝臓に悪いかどうかは、「どの種類」を「どのように飲むか」によって大きく変わります。
甘酒の種類は2種類。
日本酒を造る際に出る酒粕からできる
米麹甘酒:
米麹を発酵させて作る
酒粕甘酒は、多くの場合は砂糖を加えて甘みを調整しており、酒粕自体がアルコールを含んでいるため、甘酒自体にも微量のアルコールが残存します。
一方、米麴甘酒はアルコールゼロですが、ブドウ糖由来の糖質が多く含まれています。
どちらの甘酒を、どのくらい飲むかで「飲む点滴」か「飲む天敵」になるかが決まるのです。
甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選①酒粕(さけかす)甘酒に含まれる「微量アルコール」
甘酒が肝臓に悪いと言われる原因のひとつは、酒粕甘酒に微量に含まれるアルコールです。
肝臓はアルコールを分解する臓器で、たとえ少量でも毎日摂取すれば負担になる可能性があります。
酒粕自体は8~10%程度のアルコールを含んでいますが、水で薄めて加熱することで、最終的にはアルコール度数は1%未満におさえられます。
ただし、家庭で手作りする際に加熱不十分な場合や、市販されている商品によってはアルコール度数が1%を超えるものもあるようです。
アルコールを避けたい場合は、米麹甘酒を選ぶと安心です。
甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選②米麹(こめこうじ)甘酒の「糖質」による脂肪肝リスク
米麴甘酒はアルコールを含みませんが、米のデンプンが麹菌の酵素に分解されてできる「ブドウ糖」による「糖質」が多く、自然で優しい甘さです。
ブドウ糖は消化の必要がほとんどなく、甘酒のような液体で飲用すると体内に素早く吸収されるのが特徴です。
脳や体のエネルギーになりやすい反面、使われなかった余分な糖は中性脂肪に変換され、肝臓に貯蔵されます。
米麴甘酒を日常的に飲用すると、肝臓に脂肪が過剰に蓄えられ、脂肪肝のリスクを高める要因になります。
健康にいいというイメージのあるヤクルト1000であっても、飲み過ぎれば糖質過多となります。ヤクルト1000の記事で糖質と脂肪肝、糖尿病の関係性を詳しく解説しているので、この機会に確認しておきましょう。
甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選③「血糖値の急上昇(血糖値スパイク)」が招くインスリン抵抗性とNASH
米麴甘酒のリスクは、脂肪を肝臓に蓄えるだけではありません。
空腹時に甘酒を飲むと、ブドウ糖が素早く吸収され「血糖値スパイク」と呼ばれる血糖値の急上昇が起こることがあります。
血糖値スパイクが起こる
↓
血糖値を下げる働きをするインスリンが大量に分泌
↓
インスリンの反応が悪くなる
↓
「インスリン抵抗性」という状態に
インスリン抵抗性が続くと脂肪肝が悪化し、「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」に進行する可能性が高くなるのです。
血糖値スパイクについてはこちらで詳しく解説しているので、血糖値に関心がある方はチェックしてみてください。
甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選④「カロリー過多」で飲む点滴が天敵に!糖尿病や肥満のリスク
栄養豊富な甘酒は100gあたり76~81kcalです。
甘酒コップ一杯(約200ml)では150kcalを超え、ごはん軽く一杯分(100g)に近いカロリーです。
そのため、普段の食事に追加して飲み続けると糖質や摂取カロリーが過剰となり、肥満や糖尿病、脂肪肝などを引き起こすリスクにつながります。
特に液体は固形物よりも満腹感を得にくいため、無意識に飲み過ぎてしまいがちです。
体に良いと思っていた飲む点滴が、糖尿病や肥満のリスクを高める飲む天敵になってしまうのです。
甘酒が肝臓に悪いと言われる理由5選⑤既存の肝疾患や糖尿病を悪化させる懸念
すでに肝疾患や糖尿病にかかっている人が、良かれと思って習慣的に甘酒を飲むと、症状を悪化させる恐れがあり危険です。
日常的に酒粕甘酒を飲めば、微量ではあるもののアルコールにより肝臓に負担がかかり続けます。
また、代わりに米麹甘酒を選んでも、豊富なブドウ糖により肝臓での脂肪合成が促進され、血糖値スパイクを通じてNASHのリスクが高まります。
どちらの甘酒を選んでも、カロリー過多による肥満のリスクが高まるので、肝疾患や糖尿病などの持病がある人は医師と相談しながら適量を飲むことが重要です。
甘酒や酒粕のすごい効果!デメリットだけじゃない飲む点滴と言われるメリットを紹介
これまで甘酒のリスクを述べてきましたが、甘酒はデメリットばかりではありません。
「飲む点滴」と言われるように、栄養や成分により健康を支える側面があるのです。
酒粕の「レジスタントプロテイン」によるNASH予防効果
酒粕は、アルコールという肝臓へのリスク要因を含む一方で、NASHの予防効果が期待される「レジスタントプロテイン」も含んでいます。
レジスタントプロテインは消化されにくいたんぱく質で、腸内で脂質の吸収を抑える働きが知られています。
動物実験ではありますが、NASHに特徴的な、肝臓への脂肪沈着や細胞の肥大化、さらには肝硬変につながる線維化も抑制されることが報告されました(参考文献:酒粕成分が非アルコール性脂肪肝炎を予防|月桂冠)。
酒粕の「ベタイン」による美肌効果や肝機能をサポートする効果
酒粕は他にも、保湿効果が高く肌や髪に潤いを与える「ベタイン」というアミノ酸の一種も含まれています。
ベタインは美肌効果のほかに、肝臓に脂肪がたまるのを防ぐ働きや、脂肪を排出させる働きがあるため、脂肪肝を予防する効果が期待できます。
さらに研究ではアルコールによる肝障害を軽減する可能性も報告されており、美容と健康の両方の面でアプローチしてくれる成分です(参考文献:ベタイン|わかさ生活)。
甘酒は腸内環境を整え下痢や風邪を予防する
米麹甘酒には、腸内環境を整えるオリゴ糖や食物繊維が豊富に含まれています。
これらは善玉菌のエサとなり、腸内細菌のバランスを改善します。
また、酒粕のレジスタントプロテインなども、腸内細菌のバランスを整えるのに役立ちます。
腸が整うことで便通が改善し、免疫力の向上や風邪予防にもつながると期待されています。
甘酒は「飲み方次第」でデメリットにもメリットにもなり得る存在です。
甘酒を飲んではいけない病気は?脂肪肝や糖尿病が気になる人の正しい選び方・飲み方
甘酒はメリットもたくさんありますが、脂肪肝や糖尿病など代謝に関わる病気がある人は、習慣的に飲むのは注意が必要です。
自分の体調や病気に合わせて、種類と量を調整する必要があります。
1. 脂肪肝・肝機能の数値が気になる方
脂肪肝や肝機能の数値が気になる人はアルコールや糖質に注意が必要です。
米麴甘酒はアルコールを含まない点で安心ですが、ブドウ糖が多く含まれるため脂肪肝を悪化させる恐れがあります。
また、酒粕甘酒には肝臓を守る効果が期待されるレジスタントプロテインやベタインが含まれる一方、微量のアルコールも含むため肝疾患がある人は控えた方が無難です。
2. 糖尿病・血糖値スパイクが気になる方
糖尿病や血糖値スパイクが気になる人の場合、糖質の管理が重要です。
そのため、一般的に砂糖が添加されている酒粕甘酒は避けた方が良いでしょう。
米麴甘酒には、米のデンプンが分解されてできる「ブドウ糖」が含まれています。
ブドウ糖は体内に吸収されやすいため、特に空腹時に摂取すると血糖値が急上昇しやすくなります。
これを避けるためには、食事中や食後など他の食品と一緒に少量を取り入れると良いでしょう。
3. 健康・美容目的で飲みたい方
特別な持病がなく、健康や美容目的の場合、目的によって選び分けるのがおすすめです。
ダイエットや腸内環境を整えたい人は、満腹感を得やすいレジスタントプロテインを含む酒粕甘酒が良いでしょう。
また、美容効果を期待する場合は、米麹甘酒に含まれるビオチンにより、肌荒れ・肌のくすみなど、肌のバリア機能や保湿改善効果が期待できます。
また、ブレンドしてそれぞれの栄養を取り入れる方法もあります。
研究データから導く甘酒の「安全な1日の摂取量」と「飲むタイミング」
いくつかの研究データより、米麹甘酒を1日100ml~120ml程度の摂取であれば安全性に問題はないと報告されています(参考文献:麹甘酒の過剰摂取による安全性検証試験、麴甘酒の長期摂取による安全性検証試験)。
ただし、飲むタイミングについては多くの試験では「1日1回、決まった量を毎日飲む」というデザインで、明確な研究は多くありません。
一方で、美肌効果を検討する試験では、寝る前に飲むことで効果が確認されています(参考文献:月桂冠総合研究所)。
血糖値への影響を考慮すると、空腹時を避け、食事中や食後など他の食品と一緒に少量飲むのが望ましいでしょう。
「甘酒 肝臓に悪い」に関するよくある質問(Q&A)
Q1.薬を飲んでいるときに甘酒を飲んでも肝臓に負担はありませんか?
A1.
甘酒自体に薬との直接的な相互作用は報告されていませんが、薬は主に肝臓で分解されるため、薬と糖質過多の状態により肝臓の負担が増える可能性があります。
特に肝機能に影響を与える薬を服用中の方は、医師や薬剤師に相談しながら、摂取量を抑えることをおすすめします。
Q2.肝臓に負担をかけない甘酒の飲み方はありますか?
A2.
もっとも大切なのは「量と頻度のコントロール」です。
1回100mL程度を目安に、空腹時を避けて食後や間食として取り入れると血糖変動がゆるやかになります。
また、毎日ではなく、週に数回の飲用、糖質の少ない食事と組み合わせるなど、全体のバランスを考える工夫が肝臓の健康維持につながります。
Q3.高齢者や持病がある人でも甘酒を飲んで大丈夫ですか?
A3.
アルコールを含まない米麹甘酒であれば、多くの高齢者や慢性疾患のある方でも少量なら問題ないとされています。
ただし糖尿病、脂肪肝、高トリグリセリド血症などを抱えている場合は、糖質制限の観点から摂取量に注意が必要です。
健康状態によっては、医師と相談しながら、少しずつ取り入れる方法が安全です。
まとめ:甘酒は健康に悪いは嘘!適量で点滴に飲みすぎれば天敵に
甘酒は栄養価の高さから、適量であれば健康や美容への効果が期待される一方で、誤った飲み方をすれば健康を損ないかねません。
肝臓に悪いと言われる理由は、酒粕甘酒のアルコールや米麴甘酒の糖分、またそれに伴うカロリー過多や血糖値スパイクによるものです。
体調に合わせて適切な種類を選び、1日100ml程度の適量であれば、肝臓をサポートし健康増進や美肌効果が期待できる「飲む点滴」です。
しかし、空腹時の大量飲用は、肥満や脂肪肝、糖尿病といった生活習慣病のリスクにつながり「飲む天敵」になってしまいます。
不安がある場合は医師や管理栄養士に相談の上、正しい知識を持って毎日の健康に役立ててください。

「飲む点滴」と評される甘酒。本記事が解説するように、その恩恵は種類と飲み方次第です。豊富な栄養によるメリットがある一方で、酒粕由来のアルコールや米麹由来の糖質が、過剰摂取により肝臓の負担となる注意点も解説しています。正しい知識で、ご自身の体調に合った飲み方を知り、日々の健康管理にお役立てください。
【監修】オオサカ堂 コンテンツ制作チーム(薬剤師在籍)
関連記事
-

-
【2026年最新】スペ112とは?健康的に理想を目指すための食事と筋トレ完全ガイド
「#スペ112」TikTokやInstagramでこのハッシュタグを見るとスタイルの良いインフルエンサー達が多数表示されて、「私もあんな風になりたい」と感じている女性は増えているといいます、 10代~ …
-

-
【禁煙】おすすめアロマアイテム「ヤードム」3選!ストレスを乗り越える必需品
禁煙のときのストレスってとんでもなく辛いですよね。今回は禁煙のストレス軽減におすすめな「ヤードム」というアロマグッズを紹介します。禁煙パイポとは全然違うので、試したことがない人は要チェックです。
-

-
【薬剤師執筆】マグネシウムサプリの選び方
こんにちは。先週は骨格筋のバグであるけいれんとして起こる「眼瞼ミオキミア」や「こむら返り」がマグネシウムで治った話をしました。今回はそんなマグネシウムについて、日本人の現状や食事での補い方、またサプリ …
-

-
スペ値(スペック)とは?「スペ110が標準」の計算式に隠された罠
「スぺ110は当たり前、120で一人前」 TikTokやX、そして夜職の採用現場で、まるで絶対的なステータスのように語られる「スペック」という数字。 SNSのタイムラインに流れてくる「スぺ120達成! …
-

-
胸を大きくする方法5選!美しいバストを目指す方法を紹介
胸を大きくしたい(バストアップしたい)と思ったことのある人は多いのではないでしょうか。日常生活でバストアップを目指すことは難しいですが、形やハリを整えることは可能です。今回は、美しいバストを叶える5つの方法を紹介しています。