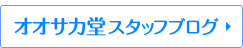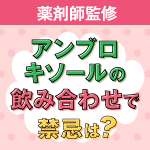2025/08/28
最近SNSで「毛穴の黒ずみがスッキリする」と話題のオロナインパック。
薬局で手軽に入手できて方法も簡単そうに見えるため、試してみたいと考えている方も多いようです。
しかし、本来の使用方法とは異なるやり方で肌に負担をかける可能性があるのをご存じですか?
本記事ではオロナイン軟膏の成分や、なぜオロナインパックが注目されるのか、そして「止めた方が良い」と言われる理由を詳しく解説します。

【ガイド】オオサカ堂 コンテンツ制作チーム
おかげさまで28年間、安心信頼の個人輸入代行・オオサカ堂のコンテンツ制作チーム。専門知識を活かし、正確で分かりやすい情報発信を心がけています。
目次
オロナインパックとは?
オロナインパックとは、傷ややけどの消毒などに使われる「オロナイン軟膏」を、鼻や小鼻まわりなどの黒ずみが気になる部分に塗り一定時間置いたあとに洗い流し、その上で市販の毛穴シートパックなどを使用する毛穴ケア方法です。
SNSを中心に「黒ずみがきれいに取れた」「安くてすぐ効果が出る」などの口コミが広がり、一気に注目度が上がりました。
ただし、本来オロナイン軟膏は殺菌や消毒が主な目的の医薬品であり、メーカーもこうした“パック”としての利用方法を推奨しているわけではありません。
いわゆる自己流のケアとして広まった経緯があるため、利用する場合は肌質との相性やリスクを十分に理解する必要があります。
オロナインパックのやり方は、一般的に以下のステップが知られています。
- 洗顔して肌の汚れや油分を落とす
- オロナイン軟膏を黒ずみが気になる部分にたっぷり塗る
- 10〜15分程度置いてから、ぬるま湯や洗顔料で落とす
- その後、毛穴パックやシートを貼り付けて角栓を除去
- パックを剥がしたら水で洗い流す・化粧水などで保湿する
ネットの口コミ上では「オロナインパックをすると、毛穴パックを剥がしたときにごっそり角栓が取れる」「気になる黒ずみをすぐに解消できる」と評判ですが、肌質によっては赤みや刺激、乾燥といったトラブルが起きる可能性も否定できません。
まずは、オロナイン軟膏そのものの成分を知ることが重要です。
オロナイン軟膏の成分
オロナイン軟膏の主な有効成分は「クロルヘキシジングルコン酸塩液」で、これは高い殺菌力を持つ成分として知られています。医薬品の分類では一般用医薬品であり、軽度の傷ややけど、水虫、ニキビなどの細菌感染を抑えるために使用されるのが一般的です。
クロルヘキシジングルコン酸塩液
細菌や真菌(カビ)などを殺菌する作用があり、感染症の予防や炎症の鎮静にも寄与します。
油性基剤(オリブ油など)
肌の乾燥を防ぐため、保湿効果もあるとされています。ただし、軟膏のベタつきが苦手という方も多いです。
このように、本来は傷口や軽い炎症部位の消毒を想定して作られた製品です。毛穴の黒ずみは角栓や酸化した皮脂が原因なので、殺菌成分が直接黒ずみを“溶かす”わけではありません。あくまで毛穴に付着した雑菌の増殖を抑える役割が中心となります。
参考文献:【公式】オロナインH軟膏|大塚製薬
口コミから広がる「黒ずみが消える」「すぐに効果が出る」イメージ
オロナインパックがここまで話題になった背景には、SNSや口コミサイトで拡散される魅力的なビフォーアフター写真や体験談があります。例えば、
- 「つけてはがしたら、角栓がびっしり取れた!」
- 「あっという間に鼻の黒ずみが目立たなくなった!」
- 「クレンジングや洗顔では取れなかった汚れがスッキリ!」
など、即効性を感じさせるような投稿は多くの人の興味を引くでしょう。特に、ドラッグストアで手軽に買える「オロナイン軟膏」を使うというハードルの低さも相まって、多くのビギナーが飛びつく結果となりました。
しかし、こうした口コミには個人差が大きく、実際に試してみて肌荒れを起こしたり、かえって毛穴が開いてしまったりするケースも少なくありません。次章では、なぜ「オロナインパックを止めた方が良い」と言われるのか、その理由を3つに分けて解説していきます。
【後悔】オロナインパックを止めた方が良い理由① 強い殺菌成分が肌に負担をかける
オロナイン軟膏には強い殺菌効果があるため、ニキビ菌や雑菌などの増殖を抑えるうえでは確かに有効ですが、肌の上に存在する常在菌まで除去してしまう恐れがあります。
常在菌は健康な肌を保つために欠かせない存在であり、過剰な殺菌が続くと肌のバリア機能が乱れ、外部刺激に弱くなって赤みや乾燥を招きやすい状態になってしまうのです。
特に、軟膏を塗って長時間放置すると、肌の水分が蒸発しやすくなるうえに成分との接触が増えて刺激が強まります。
敏感肌や乾燥肌の方であれば、ピリピリとした感覚やかゆみが出るリスクが高まりやすく、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
【後悔】オロナインパックを止めた方が良い理由② 本来の使い方ではない
オロナイン軟膏は本来、傷ややけど、ニキビなどの患部を保護・消毒するために開発された医薬品です。
しかし、鼻に塗って毛穴パックを行うという使用法は想定されておらず、メーカーも正式には推奨していません。
ここでは、製品の本来の目的とは違う方法で使うリスクや、思わぬ問題点について詳しく見ていきましょう。
オロナイン軟膏は傷や炎症部分を保護することを想定して作られた商品であり、鼻や小鼻まわりに広げてパックする使い方はメーカーの想定範囲外です。
実際、こうした自己流の使用で肌トラブルが起きても、メーカー保証の対象にはならない可能性が高く、リスクを伴う行為といえます。
また、「オロナインパックで毛穴の黒ずみが取れた」という声がある一方で、実際に黒ずみを除去しているのは毛穴シートパックの粘着力の可能性も否定できません。
要するに、オロナインが決定打というわけではないため、過剰に期待すると肩透かしに終わるだけでなく、肌への負担というデメリットの方が目立ってしまうケースがあるのです。
参考文献:【公式】オロナインH軟膏|大塚製薬
【後悔】オロナインパックを止めた方が良い理由③ 長期的な毛穴ケアには向かない
鼻の黒ずみや角栓は、皮脂や古い角質が詰まって酸化したものです。
オロナインパックで一時的に除去できたとしても、根本原因となる過剰な皮脂分泌や角質肥厚を改善しないかぎり、時間が経てばまた詰まりや黒ずみが目立つようになります。
さらに、毛穴パックで強引に角栓を引き抜く行為は、肌を傷つけたり毛穴を広げたりするリスクが高く、長期的に見たときにはむしろ毛穴が目立つ原因になりかねません。
継続してパックを行うほど肌へのダメージが積み重なるため、その場しのぎの効果を得るために繰り返し使用すると、結局は黒ずみや毛穴の開きなど、より深刻なトラブルにつながる恐れがあります。
オロナインパックで後悔したという事例
実際にインターネット上を調べてみると、オロナインパックを試した結果、以下のようなトラブル報告も散見されます。
- 「肌が赤く腫れてしまい、数日間メイクができなかった」
- 「急にヒリヒリ痛くなって慌てて洗い流したけど、鼻周りが真っ赤に」
こうした事例を見ると、その危険性に気付いて頂けたかもしれません。
即効性や手軽さを優先して安易に飛びつくと、かえって大きな肌ストレスを抱える結果になる可能性があります。
オロナインパック以外の毛穴ケア方法
オロナインパックに頼らなくても、毛穴の黒ずみや角栓をケアする方法はいくつか存在します。より肌への刺激が少なく、長期的にケアできるものを選んでみましょう。
クレイパック
泥(クレイ)には皮脂や汚れを吸着する効果があり、毛穴の詰まりを取り除くのに役立ちます。オロナインパックと違い、クレイパックは専用に開発されている製品が多く、使用方法も明確に示されているため、トラブルが起きにくいのが特徴です。
ピーリング
AHA(フルーツ酸)やサリチル酸などの成分を使ったピーリングは、古い角質を柔らかくして剥がすことで毛穴汚れを除去します。ただし、ピーリングも肌への刺激が強めなので、敏感肌の人は配合濃度や使用頻度に注意が必要です。
皮膚科でのケア
肌トラブルが繰り返される場合、やはり皮膚科の専門医に相談するのが確実です。医療機関では、ケミカルピーリングやレーザー治療など、より専門的かつ安全性を担保したアプローチが可能になります。自分の肌質や悩みに合わせて、プロの助言を得るのがおすすめです。
(参考文献:毛穴黒ずみが気になる人へ!原因と対策方法、予防のための生活習慣も解説 | 銀座アイグラッドクリニック)
オロナインパックについてよくある質問
オロナインパックはSNSなどで拡散される情報から、即効性や簡便さが注目を集めています。
しかし、その強い殺菌成分や本来の使用目的とのズレなどを踏まえると、実際に「敏感肌でも大丈夫なのか」「ニキビを治す効果はあるのか」など、気になる疑問点が多く浮かんでくるのも事実です。
ここではよく挙げられる2つの質問を取り上げ、わかりやすく解説していきます。
Q1.敏感肌でもオロナインパックを使って良いのですか?
敏感肌の方は角質層が薄くバリア機能が低下しやすいため、オロナイン軟膏の殺菌成分が逆に刺激となって肌荒れを引き起こす可能性があります。とくに、オロナインを塗った状態で長時間放置するパック方法は、肌の水分を奪いやすくなるうえに常在菌のバランスも崩れやすいのが難点です。もし試す場合は、短時間にとどめることはもちろん、洗い流した後の保湿を徹底し、赤みやヒリヒリ感を少しでも感じたらすぐに中止するようにしましょう。
Q2.ニキビを治す効果は期待できますか?
オロナイン軟膏は殺菌力があるため、軽度の炎症を抑える作用も期待できますが、鼻の黒ずみや角栓に対してパック形式で使うことで直接ニキビが治るわけではありません。ニキビはホルモンバランスや生活習慣など、さまざまな要素が絡んで悪化・再発を繰り返します。そのため、ニキビが頻繁にできる場合は、まずは皮膚科で適切な治療薬を処方してもらい、原因を根本的に改善するのが遠回りのようでいて最も確実な方法です。
参考文献:いりなか駅前皮フ科ビューティークリニック
Q3. オロナインパックを毎日続けても大丈夫ですか?
オロナインパックを毎日続けると、皮脂膜が過剰に除去され角質バリアが乱れやすくなります。殺菌成分の長期連用は常在菌バランスも崩し、乾燥やニキビ悪化を招く恐れがあるため、多くても週1回が目安。思春期や生理前は刺激に敏感なので特に注意し、使用後は低刺激の化粧水とセラミド系クリームでしっかり保湿し、紫外線対策も忘れずに行いましょう。
Q4. 鼻以外(あご・頬など)の毛穴にも効果がありますか?
あごには皮脂が多いため角栓浮きが期待できますが、頬など皮脂量が少ない部位では乾燥や赤みを起こしやすく、毛穴が逆に目立つ場合があります。あごは週1回程度で様子を見つつ、頬やこめかみは避けるか密着時間を数分に短縮し、その分保湿とUVケアでバリア機能を守ることが肌負担を軽減するコツ。冬場やエアコン環境下は事前にミスト化粧水で潤いを補うと刺激を抑えられます。
Q5. オロナインパックと角栓除去シートやピーリング剤を併用してもよいですか?
併用すると物理・化学刺激が重なり必要な角質まで剥がしてしまい、炎症性色素沈着やバリア機能低下を招くリスクが高まります。どうしても試す場合は数日空けて順番に使用し、ピーリングは夜に行い翌朝は低刺激洗顔と高保湿でアフターケアを。敏感肌・乾燥肌は併用を避け、単品ケアに留めるのが無難です。特にAHA配合製品は刺激が強いので要注意。
まとめ:オロナインパックを止めた方が良い理由!SNSで話題の毛穴ケアについて解説
SNSで話題の「オロナインパック」は、確かに手軽かつ即効性があるように見えますが、殺菌成分の強さや本来の使い方ではないリスクなど、多くのデメリットが潜んでいます。
一時的に毛穴の黒ずみが取れたように感じても、長期的なケアには不向きで、肌に過度の負担をかける可能性が高いのが現実です。
もし毛穴の黒ずみや角栓に悩んでいるのであれば、まずは日々の洗顔やクレンジングを見直し、保湿や生活習慣を整えるなどの基本ケアを地道に続けるのが大切です。
即効性を期待して強引に角栓を除去すると、その場しのぎの解決にしかならないばかりか、さらに毛穴が広がったり肌が傷ついたりする恐れがあります。
毛穴ケアの手段はほかにも多数存在します。酵素洗顔やクレイパック、定期的なピーリングなど、肌質に合わせて選べる選択肢は豊富です。
どうしても改善が見られない場合や、敏感肌でトラブルが心配な方は、皮膚科など専門機関で相談することを検討しましょう。
結論としては、オロナインパックがSNSで拡散される情報ほど“安全”かつ“即効性のある”毛穴ケアであるとは言い切れません。
肌は一人ひとり異なるため、話題に流されるのではなく、自分の肌に適したケア方法を選ぶことが美肌への近道です。
オロナイン軟膏は本来の使用目的である消毒薬として使い、毛穴ケアはより専門性のあるアプローチを取り入れて、トラブルのない美肌を目指しましょう。
(執筆・オオサカ堂 コンテンツ制作チーム)
関連記事
-

-
アンブロキソールの飲み合わせで禁忌は?咳が増えると言われる理由も解説
痰をやわらかくして排出を助けるアンブロキソールは、医療用医薬品や市販薬でも広く使われています。 医療関係者向け薬の説明書(添付文書)には、一緒に飲んではいけない薬(併用禁忌)や注意が必要な薬(併用注意 …
-

-
【2026年最新】スペ112とは?健康的に理想を目指すための食事と筋トレ完全ガイド
「#スペ112」TikTokやInstagramでこのハッシュタグを見るとスタイルの良いインフルエンサー達が多数表示されて、「私もあんな風になりたい」と感じている女性は増えているといいます、 10代~ …
-

-
ミロが体に悪いと言われる理由5選!大人が飲んだ時の効果についても解説
ミロが体に悪いと言われる理由は、1日に何本も飲むことで糖質過多になったり、カロリー過多になったりしてしまうことが原因です。通常の飲み方であれば心配する必要はありません。 1973年の発売以来、多くの人 …
-

-
禁煙すると離脱症状で気持ちいいという噂の真実!詳細について徹底解説
「禁煙に挑戦すると“離脱症状が気持ちいい瞬間がある” 確かに一部の人は、タバコを断った直後に軽い多幸感やハイな気分を経験します。 しかしその裏側では、依存脳が次の喫煙を強烈に迫る波も待っています。(参 …
-

-
【2026年最新】熱を出す方法は?前日にすると翌朝起きた時にどうなるのか徹底解説
「どうしても休みたい…」「熱でもあれば…」 学校や仕事を休むための正当な言い訳を探して、この記事にたどり着いたのかもしれません。 まず結論からお伝えすると、巷でウワサされる熱を出す方法は一時的でバレま …