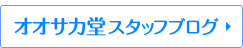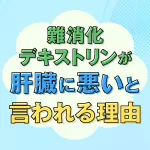2025/12/29
黒豆にはイソフラボンが豊富ですが、食品安全委員会は 「大豆イソフラボンの安全な摂取上限は 1 日 70〜75 mg」 と示しています(出典:日常の食生活の中で、大豆イソフラボンを適切に摂取する方法は?|食品安全委員会)。
また、農林水産省は黒豆原料に発生するアフラトキシンについて「総量 10 µg/kg を超える食品は流通させてはならない」と定めています(出典:農林水産省が優先的にリスク管理を進めているかび毒|農林水産省)。
この記事では、黒豆茶の基本的な情報から、気になるデメリットや具体的な注意点、そして安心して楽しむための適量や飲み方まで、詳しく解説していきます。
※本記事の内容は、診断や治療を目的とするものではありません。体調に不安がある場合は必ず医師にご相談ください。
- 黒豆茶を飲み過ぎると起こり得るデメリット
- 原料・保存に潜むリスクと安全対策
- 肝臓を守りながら飲むための適量ガイド

【ガイド】オオサカ堂 コンテンツ制作チーム
おかげさまで28年間、安心信頼の個人輸入代行・オオサカ堂のコンテンツ制作チーム。専門知識を活かし、正確で分かりやすい情報発信を心がけています。一般社団法人 薬機法医療法規格協会のYMAA資格保有者が執筆。
他の人はこちらも検索しています
目次
- 黒豆茶とは?特徴や成分について
- 黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由①大豆イソフラボンの“過剰摂取”と混同されやすい
- 黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由②肝疾患を抱える人の“自己判断で大量摂取”
- 黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由③残留農薬・カビ毒など“原料汚染”の懸念
- 黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由④薬物代謝酵素との“相互作用”の可能性
- 黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由⑤体質による“免疫性・アレルギー反応”
- 黒豆茶の一日の摂取量(適量)
- 黒豆茶おすすめの飲み方
- 黒豆茶は寝る前に飲むのがおすすめ
- 黒豆茶のデメリット!下痢と便秘に要注意
- 黒豆茶の効果はいつから
- 黒豆茶が肝臓に悪いと言われることに関するよくある質問(FAQ)
- まとめ:黒豆茶は肝臓に悪いというのは行き過ぎた話
- 出典:
黒豆茶とは?特徴や成分について
健康や美容に関心のある方々の間で注目を集めている黒豆茶。
その名の通り、黒豆を原料としたお茶ですが、具体的にどのような特徴や成分を持っているのでしょうか。
まずは、黒豆茶の基本的な情報から見ていきましょう。
黒豆茶の原料と焙煎製法
黒豆茶の主原料は、もちろん「黒豆(黒大豆)」です。黒豆の黒い皮の部分には、ポリフェノールの一種であるアントシアニンが豊富に含まれており、これが黒豆茶特有の健康効果にもつながっています。使用される黒豆の種類は様々で、丹波黒や光黒などが有名です。産地や品種によって、風味や成分にも多少の違いが出ることがあります。
製造方法は、まず良質な黒豆を選別し、丁寧に洗浄・乾燥させます。その後、黒豆の風味と成分を最大限に引き出すために重要な工程が「焙煎」です。焙煎の温度や時間、方法(直火焙煎、砂焙煎など)によって、お茶の香り、味、水色(すいしょく:お茶の色)が大きく変わってきます。
一般的には、じっくりと時間をかけて焙煎することで、黒豆特有の香ばしさと甘みが引き出され、えぐみが抑えられます。
代謝を助ける主な栄養成分
黒豆茶が健康茶として注目される理由は、その豊富な栄養成分にあります。特に、私たちの体の代謝をサポートする成分が多く含まれているのが特徴です。
まず、黒豆の黒い種皮に豊富に含まれるポリフェノールの一種がアントシアニンです。これは強力な抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素を除去する働きが期待されています。その結果、細胞の老化を防ぎ、生活習慣病の予防や眼精疲労の改善など、様々な健康効果が報告されており、代謝を促進し血液循環をサポートする役割も担っています。
次に、女性ホルモンであるエストロゲンと似た働きをすることで知られる大豆イソフラボンも重要な成分です。更年期症状の緩和や骨粗しょう症の予防、美肌効果などが期待されるほか、脂質代謝の改善にも関与し、コレステロール値を調整する働きも報告されています。
これらに加えて、黒豆にはビタミンB群(B1、B2、B6など)やビタミンE、カリウム、カルシウム、鉄分などのビタミン・ミネラル類も含まれており、これらは体の調子を整え、エネルギー代謝を円滑にするために不可欠な栄養素です。
これらの成分が複合的に働くことで、黒豆茶は私たちの健康維持や代謝促進に貢献してくれると考えられています。
黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由①大豆イソフラボンの“過剰摂取”と混同されやすい
「黒豆茶は肝臓に悪い」という噂の大きな原因は、大豆イソフラボンの「過剰摂取」問題との混同です。
これはサプリメントなど特定のケースを基にした情報が、誤って黒豆茶全体に当てはめられてしまったものです。
背景には、イソフラボンを濃縮したサプリで肝機能の数値が悪化した報告や、国がサプリ等での上乗せ摂取の上限目安(1日70~75mg)を示していることがあります。
しかし、黒豆茶1杯に含まれるイソフラボンはわずか数mg程度。
平成14年国民栄養調査(厚生労働省)によると大豆・大豆製品、醤油、みそなどの食品摂取量から試算した大豆イソフラボンアグリコン(問4参照)の摂取量は、16~22mg/日とされています。
上限に達するには非現実的な量を飲む必要があり、普通に楽しむ分には全く心配ありません。
断片的な情報に惑わされ、本来安全な健康茶を避けるのは非常にもったいないことです。
サプリと食品のお茶は別物と考え、正しい知識で判断しましょう。
参考文献:大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A | 厚生労働省
黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由②肝疾患を抱える人の“自己判断で大量摂取”
黒豆茶のリスクで特に注意したいのが、肝臓に持病がある方の「自己判断による大量摂取」です。
肝機能が低下している場合、体に良いとされるものでも、度が過ぎればかえって害になることがあります。
同じくよもぎ茶も肝臓に悪い?と噂がありますが、これも同じ理由。
自己判断でのがぶ飲みは絶対に避け、必ず事前に医師へ相談してください。
飲む場合も1日2~3杯程度を目安に、定期的な検査で安全を確認しながら付き合うことが重要です。
参考文献:黒豆茶の驚きの効果とは?成分・効能や飲む際の注意点を解説|セラピストプラス
黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由③残留農薬・カビ毒など“原料汚染”の懸念
黒豆茶の安全性は、お茶そのものだけでなく「原料の品質」に大きく左右されます。
特に注意すべきなのが、保管状態の悪い黒豆に発生することがある「アフラトキシン」という非常に強力なカビ毒です。
このカビ毒は強い発がん性と肝毒性を持ち、ごく微量でも長期間摂取し続けると、肝硬変や肝がんのリスクを高めることが知られています。
安価な輸入品の中には、残念ながら検査基準を満たさないものが流通する可能性もゼロではありません。品質が不明な製品を大量に飲み続けるのは、こうしたリスクを高める行為と言えます。
肝臓を守るための対策は、信頼できるメーカーの製品を選ぶこと。具体的には「国産」のものや、第三者機関による「カビ毒・残留農薬検査済み」と明記された製品を選ぶのが安心です。
開封後も湿気を避けて早めに使い切るなど、正しい保存を心がけましょう。
参考文献:Mycotoxins|World Health Organization
黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由④薬物代謝酵素との“相互作用”の可能性
日常的に薬を飲んでいる方は、黒豆茶との「飲み合わせ」に注意が必要です。
黒豆に含まれるポリフェノールなどの成分が、肝臓で薬を分解する特定の酵素(CYP450)の働きに影響を与える可能性が報告されています。
この酵素の働きが邪魔されると、薬の分解が遅れて体内に長く留まり、結果として薬が効きすぎて副作用のリスクが高まることがあります。逆に、分解が速まり効果が弱まるケースも考えられます。
特に、血液をサラサラにする薬(ワルファリン)、一部のコレステロールを下げる薬や血圧の薬などを服用中の方は慎重になるべきです。
「お茶だから大丈夫」「健康食品だから安全」といった自己判断は大変危険です。
常用している薬がある場合は、黒豆茶を習慣的に飲む前に必ず医師や薬剤師に相談し、安全性を確認してください。
黒豆茶は肝臓に悪いと言われる理由⑤体質による“免疫性・アレルギー反応”
ごくまれですが、個人の「体質」が原因で黒豆茶が肝障害の引き金になることがあります。
これは飲む量に関係なく起こるアレルギー反応の一種で、注意が必要です。
特に、大豆そのものにアレルギーがある方や、シラカバ・ハンノキなどの花粉症(口腔アレルギー症候群)を持つ方は、黒豆茶の成分に体が過敏に反応してしまうことがあります。
口内のかゆみや蕁麻疹だけでなく、まれにアレルギー反応が肝臓に及び、肝障害(特異体質性薬物性肝障害)に発展するケースが報告されています。
この反応は予測が難しいため、リスク管理が重要です。アレルギーの既往がある方は、まず少量(1杯)から試して体調に変化がないか観察しましょう。
もし飲んだ後に、原因不明のだるさ、吐き気、黄疸、褐色の尿などの異変を感じたら、直ちに飲用を中止し、医療機関を受診してください。
参考文献:Bean bag allergy revisited: a case of allergy to inhaled soybean dust|National Library of Medicine
黒豆茶の一日の摂取量(適量)
黒豆茶の様々な側面について見てきましたが、実際に飲む際にはどのくらいの量が適量で、どのように飲むのがおすすめなのでしょうか。
黒豆茶のデメリットを避け、メリットを最大限に活かすための飲み方について解説します。
1日の適量については、厳密な決まりはありませんが、一般的には1日に2~4杯(約400ml~800ml)程度を目安にするのが良いでしょう。
飲み始めは1日1杯程度から試し、体調に変化がないか確認しながら徐々に増やしていくのがおすすめです。胃腸が弱い方や、食物繊維の摂取に慣れていない方は、少なめの量から始めるか、薄めに煮出して飲むと良いでしょう。
また、黒豆茶だけでなく、水や他のお茶などからも水分を摂取することを忘れずに、全体の水分摂取量も考慮しましょう。
大切なのは、自分の体と相談しながら調整することです。一度に大量に飲むのではなく、数回に分けて飲む方が、成分の吸収効率も良く、体への負担も少なくなります。
参考文献:黒豆茶に期待できる6つの効能と、効果的な飲み方。飲み過ぎるとデメリットや副作用も[管理栄養士監修] |健康 ×スポーツ『MELOS
黒豆茶おすすめの飲み方
温かい黒豆茶は体を温め、リラックス効果も高まり、香ばしい香りもより引き立ちます。
特に冷え性の方や就寝前に飲む場合は温かいものがおすすめです。
黒豆の有効成分をしっかりと抽出したい場合は、やかんで煮出して飲むのが良いでしょう。5~10分程度煮出すと、色濃く、風味豊かな黒豆茶ができます。
煮出した後の黒豆は、そのまま食べたり、料理に活用したりすることも可能です。
ティーバッグタイプや粗挽きの黒豆茶であれば、急須で手軽に楽しめます。
忙しい日常の中でも取り入れやすい方法です。
夏場などには、水出しでスッキリと黒豆茶を作るのも良いでしょう。
香ばしい香りはリラックス効果も期待できるため、仕事や家事の合間の休憩時間にも適しています。
これらの情報を参考に、ご自身のライフスタイルや好みに合わせて、黒豆茶を美味しく、そして健康的に楽しんでください。
黒豆茶は寝る前に飲むのがおすすめ
ノンカフェインである黒豆茶は、就寝前のリラックスタイムにも適した飲み物として人気があります。
では、具体的に寝る前に黒豆茶を飲むと、どのような影響があるのでしょうか。
寝る前に黒豆茶を飲むメリットとしては、まずノンカフェインであるため睡眠を妨げない点が挙げられます。
コーヒーや緑茶に含まれるカフェインの覚醒作用の心配がなく、安心して飲むことができます。
また、黒豆茶特有の香ばしい香りにはリラックス効果があると言われ、温かい黒豆茶をゆっくりと飲むことで一日の緊張が和らぎ、穏やかな気持ちで眠りにつく準備ができるでしょう。
さらに、温かい黒豆茶は体を内側から温め、血行を促進し、スムーズな入眠をサポートすることが期待できます。
特に冷え性で寝つきが悪いと感じる方にはおすすめです。加えて、黒豆に含まれるGABA(ガンマ-アミノ酪酸)には、興奮を鎮めたりストレスを軽減したりする働きがあるとされ、睡眠の質の改善に関与する可能性も指摘されていますが、黒豆茶からの摂取量や直接的な効果についてはさらなる研究が必要です。
黒豆茶のデメリット!下痢と便秘に要注意
「ノンカフェインで体に優しい」「アンチエイジングに良い」として人気の黒豆茶。 香ばしくて飲みやすいため、ついつい水代わりにガブガブ飲んでしまいがちですが、体に良いはずの成分も、「摂りすぎ」れば体調を崩す原因になる点には注意が必要です。 特に胃腸がデリケートな方は、以下の症状が現れる可能性があるため、自分の体調に合わせた適量を知ることが大切です。
黒豆茶を飲みすぎると下痢をする
「黒豆茶を飲み始めたら、お腹が緩くなった」 これは、黒豆に含まれるマグネシウムやサポニンという成分の影響が考えられます。
- マグネシウムの緩下作用(かんげさよう) 黒豆に豊富に含まれるマグネシウムは、実は病院で処方される便秘薬(酸化マグネシウムなど)と同じ働きをします。腸内で水分を集めて便を柔らかくする作用があるため、過剰に摂取すると便が緩くなりすぎてしまい、下痢を引き起こすことがあります。
- サポニンの刺激 黒豆の皮に含まれるサポニンには、油を溶かす界面活性作用があり、これが腸を刺激して蠕動(ぜんどう)運動を活発にします。適度なら便通改善に役立ちますが、飲みすぎると刺激が強すぎて腹痛や下痢の原因となります。
- 食物繊維の摂りすぎ 食物繊維は便秘解消に役立つ一方で、摂りすぎるとお腹がゆるくなり何べん傾向になってしまいます。
特に、煮出した濃い黒豆茶を一度に大量に飲むと、これらの成分が一気に腸に届くため注意が必要です。
黒豆茶で逆に便秘になることも
「便秘解消のために飲んだのに、かえって詰まってしまった…」 一見矛盾しているように思えますが、実はこれにも医学的な理由があります。原因は「不溶性食物繊維」のバランスです。
黒豆茶の豆(出がらし)も一緒に食べている方は特に注意が必要です。 黒豆に含まれる食物繊維の多くは、水に溶けない「不溶性」です。これは便のカサを増やす働きがありますが、水分が不足した状態で不溶性食物繊維ばかりを大量に摂ると、便が硬くなりすぎて腸内で詰まってしまうことがあるのです。
黒豆茶の利尿作用にも注意しよう
一方で、注意点もいくつかあります。最も注意したいのは利尿作用による夜間頻尿の可能性です。黒豆茶に含まれるカリウムの利尿作用により、夜中にトイレに行きたくなって目が覚めてしまうことがあります。就寝直前ではなく少し早めの時間に少量(コップ半分~1杯程度)を飲むようにすると良いでしょう。
黒豆茶の効果はいつから
黒豆茶は飲んですぐに感じるのは、香ばしい風味とカフェインレスによるリラックス感、さらに黒豆由来サポニンの軽い利尿作用で足のむくみが引きやすくなる点です。
一方、ポリフェノールであるアントシアニンやイソフラボンが血糖やLDLコレステロールを整え、抗酸化ストレスを下げることで肌ツヤを高めるなどの体質改善効果は、毎日1〜2杯を1日おきではなく連日続けて2週間から1か月前後で表れ始めるといわれます。
加えて食事の塩分や睡眠の質にも気を配ると相乗効果が期待できるでしょう。
黒豆茶が肝臓に悪いと言われることに関するよくある質問(FAQ)
Q.1 黒豆茶は妊娠中でも飲んでいい?
基本的には、妊娠中に黒豆茶を適量飲むことは問題ないと考えられています。その主な理由は、ノンカフェインであること、そして黒豆には鉄分や葉酸、食物繊維など、妊娠中に摂りたい栄養素も含まれているためです。
ただし、いくつかの注意点があります。まず、黒豆に含まれる大豆イソフラボンの摂取量です。妊娠中の大豆イソフラボンの安全な摂取量についてはまだ明確な基準がないため、1日に何リットルも飲むような極端な飲み方は避けるべきです。
妊娠中に黒豆茶を飲む場合は、他の大豆製品とのバランスも考えながら、適量を守ることが大切です。心配な場合は、必ずかかりつけの産婦人科医や助産師に相談するようにしてください。
Q.2 黒豆茶の代替ノンカフェイン茶は?
黒豆茶の香ばしさや栄養価は魅力的だけれども、体質に合わなかったり、アレルギーが心配だったり、あるいは黒豆茶のデメリットとして挙げた点が気になってしまう…という方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合に、代わりとして楽しめるノンカフェインのお茶はたくさんあります。
代表的なものとして、まず麦茶が挙げられます。
日本では夏の定番飲料として親しまれ、大麦を焙煎して作られるため香ばしい風味とすっきりとした後味が特徴です。カフェインゼロで低カロリー、ミネラルを含み血流改善効果や抗酸化作用も期待できますが、大麦アレルギーの方は注意が必要です。
色々な種類を試してみて、ご自身のお気に入りを見つけるのも楽しいでしょう。
まとめ:黒豆茶は肝臓に悪いというのは行き過ぎた話
この記事では、栄養満点で香ばしい黒豆茶について、気になる「黒豆茶のデメリット」や「肝臓に悪い」という噂の真相、そして安心して楽しむための飲み方などを詳しく解説しました。
注意点を理解し、自分の体質に合わせて適量を守れば、黒豆茶のデメリットは避けることができます。黒豆茶はノンカフェインで栄養も豊富、リラックスしたい時にもぴったりな魅力的なお茶です。
この記事が、黒豆茶の正しい知識を深め、安心して楽しむきっかけになれば嬉しいです。ぜひ、あなたの生活に黒豆茶を取り入れてみてください。
出典:
限定吸水による黒千石大豆の退色抑制とその豆ごはんの官能評価|©国立研究開発法人科学技術振興機構 [JST]
ビルベリー由来アントシアニンが目に与える機能性|岐阜薬大学術リポジトリ
冷たい飲み物を飲むと下痢になるのは何でなの?|福岡天神内視鏡クリニック消化器福岡博多院
過敏性腸症候群の人が知っておきたい食べてはいけないものとは?医療のプロが徹底解説|福岡天神内視鏡クリニック消化器福岡博多院
【解説】加工食品のアレルギー表示の読み方|独立行政法人環境再生保全機構
アナフィラキシー症状を呈した豆乳による口腔アレルギー症候群の一例|©国立研究開発法人科学技
腎臓病の話 カリウムについて(1)|腎臓内科|北海道医療センター
血中イソフラボン濃度と肝がん発生との関連|国立研究開発法人 国立がん研究センター
(執筆・オオサカ堂 コンテンツ制作チーム)

黒豆茶は抗酸化成分が豊富で日常の水分補給に適しますが、カリウム豊富のため腎機能低下や利尿薬服用中の方は過剰摂取に注意。市販品でも糖分・塩分添加の有無を確認し、1日500ml程度を目安にバランス良い水分摂取を心掛けましょう。特に妊娠中や大豆アレルギーがある場合は医師へ相談の上少量から試すと安心ですね。
関連記事
-

-
オロナインパックは止めた方が良い理由!後悔する前に知るべき3つの代償
最近SNSで「毛穴の黒ずみがスッキリする」と話題のオロナインパック。 薬局で手軽に入手できて方法も簡単そうに見えるため、試してみたいと考えている方も多いようです。 しかし、本来の使用方法とは異なるやり …
-

-
禁煙の離脱症状でふわふわしてきたら何のサイン?禁煙実行マニュアル
「禁煙 離脱症状 ふわふわ」—この検索ワードにたどり着いたあなたは、禁煙に初挑戦する20〜30代のビジネスパーソンかもしれませんね。 「頭がふわふわする」「めまいがする」といった症状に戸惑い、もしかし …
-

-
【2026年最新】高菜が体に悪いと言われる理由5選!栄養成分や注意点について解説
インターネット上には「高菜が体に悪い」という情報も散見され、美味しくても控えるべきなのかと迷うかもしれません。 しかし、本当に高菜は体に悪いものなのでしょうか? 実は、その噂には誤解も多く含まれていま …
-

-
【家にあるもの】脇の黒ずみをとる方法4選!黒ずみの原因や予防方法も紹介
肌の露出が増える季節、脇の黒ずみに悩む方は多いのではないでしょうか。この記事では、脇の黒ずみができてしまう原因と対策、すでにできてしまった黒ずみをとる方法3つをご紹介します。この記事を参考に、自分に合った解決方法を探してください。
-

-
【2026年最新】難消化性デキストリンが肝臓に悪いと言われる理由5選!発がん性などについて徹底解説
「難消化性デキストリン」と商品の裏表示で見て、「これは安全なの?」「“危険”や“発がん性”という噂を聞いたけど…」と不安に思ったことはありませんか? まず結論からお伝えすると、通常の量を摂取して「難消 …