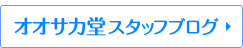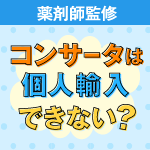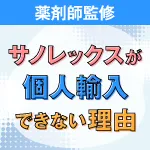2026/02/20
「トレハロースに発がん性はある?」
結論から言えば、その懸念に科学的根拠はありません。
国連の専門家委員会 JECFA は2000 年の評価でトレハロースを「ADI※設定不要=無毒性」扱いとし、安全性を確認しています。(参考文献:TREHALOSE|WHO)
本稿ではトレハロースの〈危険デマ〉が拡散した背景を分解し、国際機関の評価とメリット、上手な使い方までをわかりやすく解説します。
※本記事の内容は、診断や治療を目的とするものではありません。体調に不安がある場合は必ず医師にご相談ください。

【監修】オオサカ堂 薬事チーム
当社に在籍する薬剤師が豊富な経験を活かして医薬品情報を厳格にチェック。分かりやすい薬学的アプローチで解説しています。一般社団法人 薬機法医療法規格協会のYMAA資格保有。

【ガイド】オオサカ堂 コンテンツ制作チーム
おかげさまで28年間、安心信頼の個人輸入代行・オオサカ堂のコンテンツ制作チーム。専門知識を活かし、正確で分かりやすい情報発信を心がけています。一般社団法人 薬機法医療法規格協会のYMAA資格保有者が執筆。
目次
【結論】トレハロースに発がん性は確認されていない
「トレハロースに発がん性がある」という噂がインターネット上などで見られますが、これは科学的根拠のない明確な誤りです。
まずはじめに、トレハロースは人工甘味料ではなく天然の糖のひとつです。ダイエットブームや健康意識の高まりから、さまざまな人工甘味料が世の中に広く知られるようになり久しいです。そんな中で「トレハロース」の認知も広まっていったため、人工甘味料として認識している方もいるかもしれませんがこれは誤りです。
そしてトレハロースの安全性は、国際的な食品安全の専門機関によって、非常に高いレベルで確認されています。発がん性を示すような信頼できる研究報告は、これまでありません。
食品添加物として流通しているトレハロースは工業的に生産されたものではありますが、トレハロース自体はきのこや酵母など、私たちが古くから食べてきた多くの食品に含まれる天然の糖質であり、長い食経験に裏打ちされた安全な物質なのです。
国際機関によって安全性が確認されているトレハロースと同様に、私たちの身の回りにある食品成分の安全性は厳格な基準で評価されています。発がん性の噂などに対する科学的な見解と、安全基準であるADI(許容一日摂取量)の考え方を知ることで、食への不要な不安をなくすことができます。
JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会)の評価
トレハロースの安全性を語る上で、最も重要なのがJECFA(ジェクファ)による評価です。
JECFAとは、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で設立した、食品添加物の安全性評価を専門に行う国際的な組織です。その評価は世界で最も権威があるとされ、各国の食品安全基準の策定における科学的根拠となっています。
そのJECFAは、トレハロースの安全性について、「ADI(一日摂取許容量)を設定特定しない」という評価を下しています。「ADIを設定しない」とはつまり、「たくさん食べても体に害が出ないほど安全だから、上限を決める必要がない」という専門家の判断です。
国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)の評価
医薬品や食品のほか、生活環境中のあらゆる化学物質について、その品質、安全性と有効性を正しく評価する機関である日本の「国立医薬品食品衛生研究所」も、トレハロースの安全性についてさまざまな試験・研究を行っています。
発がん性に関係する項目としては、「変異原性試験」としてAmes 試験、染色体異常試験、 in vivo 小核試験の3つが実施されており、全て陰性と報告しています。
(参考文献:TREHALOSE|WHO、既存添加物の安全性評価に関する調査研究報告書)
他の人はこちらも検索しています
トレハロース 発がん性デマが広まった理由① 「添加物=危険」という先入観
多くの人が食品表示のカタカナ名を見るだけで、「添加化学物質=有害」と感じてしまう心理的なバイアスが存在します。
これは、トレハロースのような成分が厳しい安全性評価をクリアしていることや、どんな物質も量によって影響が異なる「用量依存性」の概念が十分に知られていないためです。塩も水も、適量は体に必要ですが、摂りすぎれば体に害──それが「用量依存性」です。
こうした知識の欠如が、科学的根拠のない漠然とした不安を増幅させ、デマが広まる土壌となってしまいます。
トレハロース 発がん性デマが広まった理由② きのこ等に含まれる天然成分であることの認知度が低い
トレハロースは、実はシイタケやパン酵母、海藻類にもごく自然に含まれている糖質の一種です。
しかし、工業的にはでんぷんを原料に酵素を使って量産されるため、法律上は「食品添加物」に分類されており、「人工甘味料」と誤解されやすい素材でもあります。
その由来が自然界にあるという事実が広く知られていれば、多くの人が抱く危険なイメージは大幅に減るはずです。
(参考文献:食品中のトレハロース含量|国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) )
トレハロース 発がん性デマが広まった理由③ バズ狙い記事で危険と煽る見出し商法
「【警告】絶対に食べるな!あの〇〇は危険!」といった刺激的なタイトルは、内容の真偽に関わらずクリックされやすく、SNSなどで瞬く間に拡散されがちです。
トレハロースも、こうした記事で根拠なく危険な添加物としてリストアップされることがあります。
しかし、元になった論文をたどると、非現実的な量を投与した動物実験だったり、全く別の物質の話だったりするケースも少なくありません。
トレハロースのメリットを整理
トレハロースの健康面での大きなメリットは、血糖値の上昇が砂糖に比べて緩やかで、インスリンの急激な分泌を抑制する点です(低GI)。
また、優れた保水力やでんぷんの老化を防ぐ作用があるため、パンをしっとりさせたり、冷凍ご飯の食感を保ったりと、食品の品質を向上させます。
さらに、虫歯菌がエネルギー源として利用しにくい性質を持つため、口腔衛生面でも利点がある糖質です。
(参考文献:糖質と虫歯の関係は?|こころ歯科)
血糖値スパイクを抑える「低GI」甘味料
トレハロースは低GI値が特徴です。GIとは「グリセミック・インデックス」のことを指し、「食品を食べた後に血糖値がどれだけ速く上がるかを示す指標」で、数値が高いほど血糖値スパイク(血糖値の乱高下)を起こしやすいことを意味します。
トレハロースのGI値は約30とされ、砂糖(GI値約60〜65)の約半分です。ゆっくりと消化・吸収されるため、血糖値スパイクを起こしづらく、食後の眠気・倦怠感、集中力低下、老化や生活習慣病のリスクなどを抑えられる点は健康上のメリットになります。
砂糖の1/2量置き換えで甘味・保湿のバランスを取る
トレハロースの特徴として、「甘味度は砂糖の約45%と上品ですっきりしている」ことと、「保水力により食品をしっとりさせる力がある」ことが挙げられます。
そのため、レシピの砂糖を全て置き換えると甘さが物足りなくなることがあります。
おすすめは、砂糖の半量をトレハロースに置き換える方法です。
例えば砂糖100gなら「砂糖50g+トレハロース50g」とすることで、甘さを保ちつつ、緩やかな血糖上昇により体への負担や食後の眠気を抑え、しっとり食感の向上を得られます。
1回10 g・1日30 g以内を目安に段階的に導入する方法
トレハロースは、一度に多量摂取すると体質によってはお腹が緩くなることがあります。
これは摂り過ぎることで吸収や消化が追いつかないために起こるもので、毒性に起因する症状ではありません。
安全に利用するためには、まず1回の摂取量を10g以下、1日の合計も30g以内を目安にし、少量から体を慣らしていくのがおすすめです。
料理や飲料に少しずつ分散させれば、快適に取り入れられます。
トレハロース発がん性に関するよくある質問
Q1. 妊婦・乳幼児が摂っても安全?
国際的な安全評価(JECFA)でも年齢制限はなく、通常の食品に含まれる範囲であれば、妊婦さんや乳幼児が摂取しても問題ないと考えられます。トレハロースはきのこやパンにも含まれる天然の糖質です。ただし、甘味への依存を防ぐため、離乳食などに使う際はごく微量から様子を見るなど、量を控えめにするとより安心です。
(参考文献:トレハロースの安全性 | TREHA Web -トレハウェブ-)
Q2. 糖尿病・ダイエット中でも使える?
血糖変動が砂糖より穏やかなため(低GI)、砂糖の代替として適しています。医師や管理栄養士の指導のもと、食事全体の糖質量を管理しながら上手に活用するのが良いでしょう。ただし、後述の通りカロリーは砂糖と同等にあるため、非糖質系の甘味料とは区別し、総摂取エネルギーの管理は必須です。
Q3. カロリーはありますか?太る原因になりますか?
カロリーは砂糖と同じ1gあたり約4kcalです。そのため、ヘルシーなイメージで使いすぎると当然太る原因になります。甘味度が砂糖より低いため、同じ甘さにしようとすると使用量が増え、かえって高カロリーになる可能性も。砂糖の一部を計画的に置き換えることで、カロリーと血糖負荷を上手に抑えることができます。
(参考文献:トレハロース|株式会社 サクラ・ノーリン)
まとめ:トレハロースに関する発がん性の噂はデマ
JECFAをはじめとする国際機関は、トレハロースを「ADI(一日摂取許容量)を特定せず」という最も安全な区分に評価しており、発がん性を示す信頼できるデータは存在しません。
デマの背景には、添加物への先入観や不安を煽るネット記事があります。
トレハロースに関する正しい情報を理解し、その優れた特性を安心して活用してください。

砂糖の代わりに使われる甘味料には、トレハロースをはじめ、オリゴ糖、羅漢果エキス、キシリトールなどさまざまな種類があり、用途や健康目的に応じて選ばれています。食品の安全性について関心を持つことはとても大切です。疑問や不安が出てきた際は、イメージや噂に流されることなく、科学的な根拠や信頼できる情報をもとに判断していくことで、より健康的な選択につながります。本稿が健康意識の高い読者の皆様の一助になれば幸いです。
監修・オオサカ堂 薬事チーム
関連記事
-

-
【薬剤師監修】オゼンピック(セマグルチド)は個人輸入できる?私たちオオサカ堂での取り扱い状況について
「ダイエットに効く」と話題のオゼンピック。(参考文献:一般名:セマグルチド (遺伝子組換え)|KEGG DRUG Database) 個人輸入は禁止されていませんが、オオサカ堂では取り扱いはありません …
-

-
【薬剤師監修】イソトレチノイン(アキュテイン)の個人輸入|オオサカ堂で注文できない理由とは
オオサカ堂でイソトレチノイン(アキュテイン)は注文できません。 注文不可の重要理由 🚫 取り扱いなし オオサカ堂では注文不可 📄 厳格な規制 厚生労働省の確認が必要 ⚖️ 法的リスク 書類なしの輸入は …
-

-
【薬剤師監修】乳酸アシドーシスの症状は?リスクを高める5つの危険因子も解説
乳酸アシドーシスの初期症状(吐き気などの消化器症状、だるさ、筋肉痛)が生じた場合は、すぐに受診が必要です(参考文献:乳酸アシドーシスについて)。 あなたが糖尿病のお薬(メトホルミン)を服用中であれば、 …
-

-
【薬剤師監修】コンサータは個人輸入できない?私たちオオサカ堂で注文できない理由を解説
「もしかして、コンサータってネットで簡単に買えるんじゃないの?」ADHDの治療を受けている方や、お子さんのことで悩んでいる保護者の方なら、一度はそう思ったことがあるかもしれません。 しかし、結論から申 …
-

-
【薬剤師監修】サノレックスの個人輸入はやばい!オオサカ堂で注文できない理由を解説
サノレックスの個人輸入は法律で禁止されており、できません。 「過去に何度もダイエットしてきたけれど、どうしてもうまく行かなかった。」 この記事を読まれている中には、このような経験をされた方もいるのでは …